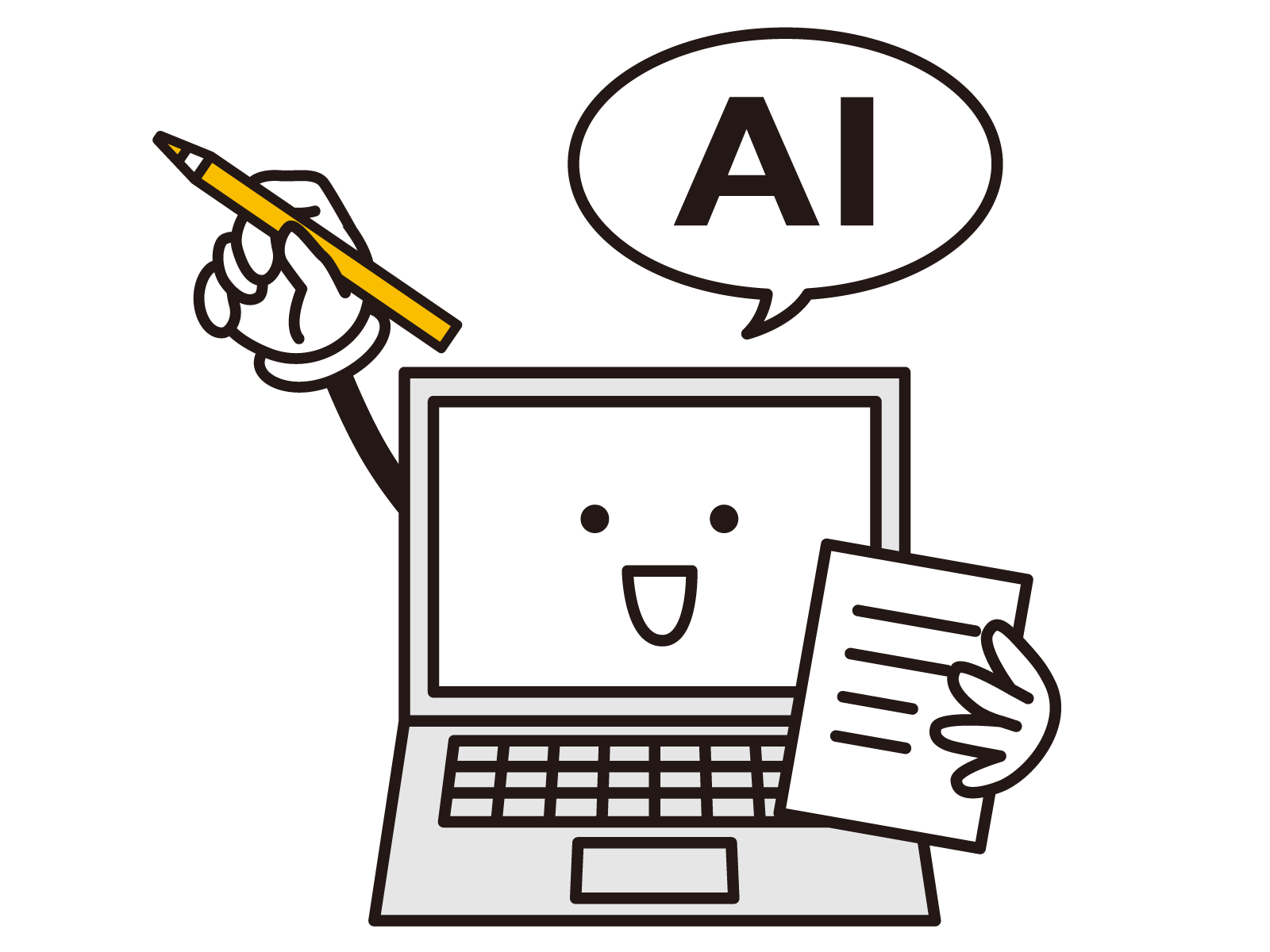2025/09/02
生成AIの時代に「失敗する力」をどう育てるか
東京都渋谷区で小学生を対象としたプログラミング教室を運営している福井です。ChatGPTをはじめとする生成AIが登場し、社会のさまざまな分野に変化をもたらしています。
これまで人間しかできないと考えられてきた作文や翻訳、プログラムの作成まで、AIが瞬時に処理してしまうようになりました。こうした現実を目の当たりにして、「子どもたちは何を学ぶべきなのか」「AIに負けない力とは何か」という不安や疑問を、多くの保護者が抱いています。私自身も教育現場で子どもたちと向き合う中で、この問いに真剣に向き合ってきました。
AIは間違えないのか
AIの特徴は、データとアルゴリズムに基づいて効率的に正解へとたどり着くことにあります。たとえば算数の問題を解かせれば瞬時に答えを出し、文章の要約も迷うことなく行います。しかし、その「正しさ」はあくまでもプログラムの範囲に収まったものです。
AIが出す誤りは、人間が悩んだ末にたどり着く失敗とは質が違います。人間の失敗には、迷い、仮説、工夫といったプロセスが含まれており、その中から新しい発想や創造が生まれます。AIには「悩む」という行為がなく、だからこそ「失敗する力」を持つ人間の価値は揺らがないのです。
失敗を恐れる子どもたち
教育現場で長年子どもたちを見てきて感じるのは、年齢が上がるにつれて失敗を恐れるようになる子が増えていることです。幼児期には積み木を崩しても笑っていた子が、小学校に入ると「間違ったら恥ずかしい」と考えるようになります。
ある男の子は算数の文章題で手が止まってしまい、「わからないからやりたくない」と言いました。しかし、彼は本当にわからないわけではありませんでした。
正解を書けなかったら先生に叱られる、友達に笑われる、そんな不安が彼の手を止めていたのです。教育が「間違えないこと」を重視してきた結果、子どもたちは挑戦する前に自分でブレーキをかけてしまうようになっているのです。
失敗から生まれる偉大な成果
歴史を振り返ると、失敗から大きな成果を得た事例は数え切れません。2002年にノーベル化学賞を受賞した田中耕一さんは、実験中に別の粉末を誤って混ぜてしまったことがきっかけで発見を成し遂げました。
アインシュタインも数多くの論文で誤りを含んでいたといわれますが、それでも最終的に革新的な理論を築きました。Facebookのマーク・ザッカーバーグやAmazonのジェフ・ベゾスも、数えきれないほどの失敗を繰り返しながら事業を成長させています。
彼らが共通して持っていたのは「失敗を恐れず挑戦し続ける力」でした。AIは正確で速いかもしれませんが、こうした人間的な遠回りからしか生まれない成果があるのです。
プログラミング教育が教えてくれること
プログラミング教育は、まさに「失敗する力」を育てる最良の場です。プログラムは一度で正しく動くことはまずありません。エラーが出たり、意図しない動きをしたりするのが当たり前です。
ある生徒は「バグが出るのは嫌だ」と言いながらも、少しずつ修正を繰り返していました。最初は半泣きになりながら取り組んでいた彼が、最後に自分のプログラムを正しく動かしたとき、満面の笑顔を見せたのを私は忘れられません。
その喜びは、正解を一瞬で示してくれるAIからは決して得られないものです。失敗を繰り返し、自分で答えを見つける過程こそが、子どもの学びを深めるのです。
回復力の大切さ
失敗した後に立ち直る力――回復力――は、これからの時代を生き抜くために欠かせません。ある女の子は、同じ課題に三日間つまずき続けました。普通なら心が折れてしまっても不思議ではありません。
しかし彼女は、エラーの原因を少しずつ探し、試行錯誤を重ね、ついには自力で解決しました。そのときの達成感と自信は、その後の学びに大きな影響を与えました。
失敗から立ち上がる経験を積み重ねた子どもは、どんな壁に直面しても前に進む力を持つようになります。これがAIの時代に人間が必要とされる力のひとつなのです。
保護者の役割
では、家庭で保護者にできることは何でしょうか。私は「先回りしない」ことだと考えています。子どもが問題に悩んでいると、つい答えを教えたくなる気持ちはよくわかります。しかし、その瞬間に子どもは自分で考える機会を失ってしまいます。
大人ができるのは、「どうすればいいと思う?」と問いかけ、子どもが考えを深める時間を待つことです。失敗を経験する時間を保障することこそが、将来の大きな力につながります。
また、失敗を「恥」として扱わず、「経験」として受け止める文化を家庭に根付かせることも大切です。子どもが挑戦した結果うまくいかなかったときに、「よく頑張ったね」と声をかけてあげるだけで、失敗は前向きな学びへと変わります。
教師に求められる姿勢
教育現場においても、教師が「失敗を認める姿勢」を示すことが欠かせません。私は授業で「間違ってもいいから答えてみよう」と声をかけています。すると、子どもたちは二つのタイプに分かれます。
適当に答える子と、本気で考えた上で答える子です。後者は間違えても力がついていきます。教師は正解を与えるのではなく、考えるためのヒントを示す存在であるべきです。AIが正解を簡単に与えてくれる時代だからこそ、人間の教師が子どもと共に悩み、考え、失敗を分かち合うことが重要なのです。
文化としての「失敗」
日本社会には「恥の文化」があります。失敗を隠そうとする傾向が強く、学校でも企業でも同じです。しかし、この考え方のままではAI時代に対応できません。むしろ失敗を積極的に公開し、学びに変える姿勢が必要です。
トヨタ自動車が現場で「失敗は改善の機会」と捉えているのは有名な話です。教育もまた同じで、失敗を否定するのではなく、そこから改善へとつなげていく文化をつくることが求められています。子どもたちに「失敗は悪いことではない」と伝えるだけでなく、大人自身も失敗から学ぶ姿を見せることが大切です。
まとめ
生成AIは、人間に「正解を出す力」では勝ち目がないことを突きつけています。しかし、失敗を繰り返し、そこから学ぶ力は人間にしかありません。子どもたちが挑戦を恐れず、失敗しても立ち上がれるようにすることが、これからの教育における最大の課題だといえます。
保護者や教育者は、子どもたちが安心して失敗できる環境を整え、その過程を共に喜び合う存在でありたい。AIに使われるのではなく、AIを使いこなす大人に育てるために、今こそ「失敗する力」を子どもたちに贈っていきましょう。
プログラミング教室スモールトレインでは、プログラミングと小学生対象の学習指導を行っています。オンラインでの指導も行っていますので、ご興味のある方はこちらからお問い合わせください。