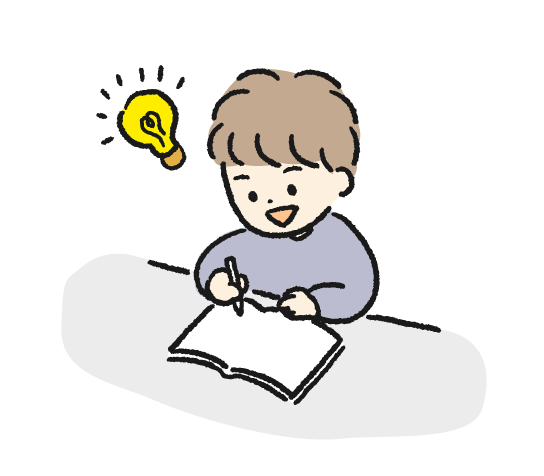2025/09/09
「できる」と「わかる」は違う――学びの本質を考える
東京都渋谷区で小学生を対象としたプログラミング教室を運営している福井です。授業をしていると、子どもたちが「できること」と「わかっていること」を混同している場面にしばしば出会います。
テストで正しい答えを書ければ安心し、それで学びを終えてしまう。しかし本当に大切なのは、その答えに至るまでの理解です。「できた」と思っていることと「わかった」と実感することの間には、明確な違いがあるのです。
正解を出すことが目的になっていないか
例えば算数の文章題で「10個のあめを5人で分けると一人何個か」という問題が出たとします。多くの子は「10÷5=2」と答えます。ここまでは「できている」状態です。しかし「なぜ割り算になるのか」と尋ねると答えられない子が少なくありません。掛け算の逆だから、という表面的な説明しかできない場合もあります。これは「わかっている」状態には達していない典型的な例です。
こうした違いを放置していると、応用力に大きな差が出てきます。掛け算か割り算かを選ぶ必要がある文章題に出会ったとき、計算だけ覚えている子は迷ってしまいます。一方で「なぜ割り算なのか」を理解している子は、状況に合わせて正しく判断できます。つまり、「できる」ことはその瞬間の点数にはつながっても、「わかる」ことがなければ未来の学びにつながらないのです。
〇と×の思考が生む弊害
学校教育では、どうしてもテストの点数に目が向きます。〇が多ければ良い、×が多ければ悪いという評価の仕方は当然のことのように思われています。しかし、それが子どもたちの思考に大きな影響を与えています。点数を取るために「当てはまる答え」を探すことばかりに集中し、「なぜそうなるのか」を考える習慣が薄れていくのです。
国語の記述問題を例にとるとわかりやすいでしょう。「自分の考えを書きなさい」と問われたとき、子どもは「先生に〇をもらえる言葉」を探しがちです。内容よりも正解っぽい表現を優先するため、自分の意見を深めることを避けてしまいます。結果として「できた」という満足感は得られても、「わかった」という理解には到達できません。
教室で見える「できる子」と「わかる子」
私がプログラミングの授業をしていてよく出会うのは、「できた」と自信を持って報告する子どもたちです。ある生徒は、見本を真似してキャラクターを動かすプログラムを完成させ、「先生、できました!」と誇らしげに言いました。
確かにその瞬間、プログラムは動きました。しかし条件を少し変えると、途端に動かなくなってしまったのです。修正を求めても、なぜ動かなくなったのかを説明できず、再び組み立て直すこともできませんでした。
このような場合、子どもは「できた」状態にはあっても、「わかっている」状態にはありません。コードの意味や処理の流れを理解していれば、変更にも柔軟に対応できます。しかし、単なる模倣や暗記に終始してしまうと、少しの変化にも対応できなくなってしまうのです。
「なぜ」を問い続けることの大切さ
教育の本質は「なぜ」を問い続けることにあります。ある国語の授業で、私は子どもに「なぜこの答えになるのか」を説明させました。最初のうちは「先生がそう言ったから」「本に書いてあったから」といった答えしか返ってきません。しかし、繰り返し問いかけていくうちに、少しずつ自分の言葉で理由を語れるようになっていきます。
「なぜ」を考えることは、時間のかかる作業です。答えを出すスピードを競うのではなく、答えに至るまでの過程を大切にする。これこそが「できる」から「わかる」へと学びを深める鍵なのです。
忘れられがちな「応用力」
中学受験を控える子どもたちを見ていると、パターンを暗記して解けるようになる子が少なくありません。確かに過去問の類題が出れば得点できます。しかし少しひねった問題が出ると対応できないことも多い。なぜなら、答えの根拠を理解していないからです。
プログラミング教育では、同じ課題でも子どもによって解き方が異なります。ある子は繰り返し処理を使い、別の子は条件分岐を工夫する。どちらも正解ですが、その違いを理解している子ほど応用力が伸びます。教育において大切なのは、答えそのものではなく、答えを導くための考え方なのです。
「できる」だけで満足してしまう危うさ
点数が取れることはもちろん励みになります。しかし「できる」ことだけで満足してしまうと、学びが停滞してしまいます。私は以前、理科の一問一答を赤ペンで埋めて提出する生徒を見たことがあります。
彼は「宿題はできました」と胸を張りましたが、実際には内容を理解していませんでした。見かけ上は「できている」ように見えても、本質的には「わかっていない」のです。
このような学び方を続けていると、後に大きな壁にぶつかります。応用問題や記述問題に対応できなくなり、急に成績が伸び悩んでしまうのです。
AI時代に求められる学び
生成AIは、膨大な知識を瞬時に検索し、正解を提示してくれます。その点では人間は到底かないません。だからこそ、人間に求められるのは「できる」ことではなく「わかる」ことなのです。
算数の計算ができるだけでなく、文章題の場面で「掛け算か割り算か」を自分で判断できること。国語の答えを単に写すのではなく、自分の考えを言葉にできること。プログラミングでコードを完成させるだけでなく、処理の意味を理解し応用できること。これらこそが、AIにはできない人間の力です。
保護者へのメッセージ
保護者の方々にお願いしたいのは、お子さんが正解したかどうかだけに目を向けないでほしいということです。「どうしてそう考えたの?」と問いかけるだけで、学びは一気に深まります。
間違えていても、その理由を自分の言葉で説明できれば大きな成長です。正解か不正解かよりも、理解に至る過程を評価すること。それが子どもの学びを支える一番の方法です。
まとめ
「できる」と「わかる」は似ているようで、まったく異なる概念です。できることは点数に直結しますが、わかることは将来の学びを支える力になります。教育現場では正解を重視せざるを得ない部分がありますが、だからこそ家庭や塾で「なぜ」を問い続ける姿勢が大切です。
生成AIの発達によって、正解を出すことの価値はますます低下していきます。その一方で、「わかる」ことの価値は高まり続けるでしょう。子どもたちがAIに使われるのではなく、AIを使いこなす存在になるために、私たち大人が育てるべきなのは「わかる力」なのです。
プログラミング教室スモールトレインでは、プログラミングと小学生対象の学習指導を行っています。オンラインでの指導も行っていますので、ご興味のある方はこちらからお問い合わせください。